|
錦糸小学校 (錦糸1- 9-12)
太平 |
錦糸小学校 (錦糸1- 9-12) 1918年 ・東京市太平尋常小学校を開設する。(錦糸小学校の誕生) この彫刻の作者はアメリカ人のローレン・マドソンさんです。今回の作品が日本での初めての作品であり、作成モチーフは音楽と美術の相互関係に着目して、音楽の「ヘ音記号」を複写し、逆さにした二つの組み合わせで、相互につながりと連結性を持たせ、塔につながる5本のケーブルは五線符を表しています。また、タイトルは作品の構成する二つの記号がお互いに反響しあっているイメージで「エコー」と名づけられました。
開校 大正 7年11月 1日
校地面積 3949㎡
通学区域
江東橋2丁目19番(JRアパート)
錦糸1丁目全域
錦糸2丁目全域
錦糸3丁目全域
錦糸4丁目全域
太平1丁目1番~16番
太平2丁目1番~9番
太平3丁目1番~10番
太平4丁目1番~4番
錦糸中学校へ
江東橋4丁目全域
竪川中学校へ
あゆみ
太平町1丁目50番地(現在の横川1丁目)
1923年 ・関東大震災で校舎が大破。火災で校舎や校具が全て焼けてしまう。
1924年 ・仮校舎ができる。
1928年 ・錦糸公園ができる。
・仮校舎を移す。(現在の太平1丁目)
1929年 ・現在の場所に、新しく鉄筋コンクリート造り3階建ての校舎ができる。
1933年 ・開校15周年記念式典を行う。校歌・校旗ができる。
1941年 ・東京市錦糸国民学校と名前が変わる。義務教育8年に延長される。
1943年 ・東京都錦糸国民学校と名前が変わる。
1945年 ・東京大空襲で、本所地区は全て焼けてしまう。
1946年 ・もとの茅場小学校を仮校舎として授業をはじめる。
1947年 ・東京都墨田区立錦糸小学校と名前が変わる。
1953年 ・開校35周年記念式典を行う。
1955年 ・東京都給食指定校となる。
1959年 ・緑のおばさん(学童擁護員)が配置される。
1962年 ・学校給食優良校として、文部省大臣より表彰される。
1963年 ・プールができる。
・日曜日の校庭開放が実施される。
1964年 ・集団登校が始まる。
1966年 ・通学帽が決められる。
・上履きを廃止する。
1967年 ・学校の住所が、墨田区錦糸1-9-12と改められる。
1968年 ・水泳教育で、NHKテレビに出演する。
・開校50周年記念式典を行う。
1971年 ・校舎の取り壊しが始まる。
1973年 ・校舎改築の工事が完了する。
・開校55周年記念式典を行う。
1978年 ・あわの自然学園ができ、移動教室が始まる。
・開校60周年記念式典を行う。
1979年 ・60周年記念として、タイムカプセルをうめる。
1981年 ・東京都教育委員会、日本学校安全会東京都支部より、東京都学校安全優
良校として表彰される。
1983年 ・開校65周年記念式典や子どもまつりを行う。
1988年 ・開校70周年記念式典や子どもまつりを行う。
1989年 ・特色ある学校づくりとして、体力づくり研究奨励校になる。
1993年 ・開校75周年を記念して、錦糸グラウンドで大運動会を行う。記念式典を行
う。
1997年 ・ランチルームができる。
・すみだトリフォニーホールがオープンし、オーケストラ教室が行われる。
・墨田区小学校研究奨励校(国語科書写)の発表をする。
1998年 ・開校80周年を記念して、学芸会を行う。記念式典を行う。
タイムカプセル
60周年記念として、校庭に埋められたタイムカプセルが10月13日、25年ぶりに開封されることになった。当初、21世紀を迎える2001年に開封する予定だったが、不況や再開発などで多くの関係者が地元を離れ、宙に浮いていた。
しかし、当時の教員らが相次いで他界する事態に、『今開かなければ、永久にその機会を逃がしてしまう』と危機感を募らせた人々が改めて、開封を思い立ったという。関係者は『25年という時間を当時の児童、関係者で分ち合いたい』と話ている。
同校のPTAが中心となって、タイムカプセルを埋めたのは同校創立60周年の1978年度。長さ1.5m、直径60㎝のジュラルミン製ケースに、在校生約830人の写真のほか、給食献立表やJR錦糸町周辺の写真、付近で売り出されていたマンションのチラシなど、当時の地域の様子を示す資料を詰め込み、校庭の南側花壇の一角に埋めた。
新世紀を迎えた一昨年に開封する計画だったが、コンサートホールやホテルを建設する同駅北口再開発事業に伴い、タイムカプセルにかかわった多くの住民が入れ替わった。さらに、当時のPTA関係者が経営していた町工場が長引く不況で苦境に陥るなどしたため、開封計画も半ば忘れられていた。
しかし、その後、計画を覚えていた当時の在校生の問い合わせが同校に相次いだり、当時の教員やPTA関係者から「このままではカプセル自体、忘れてしまう」という声が上がった。昨年夏には、『タイムカプセル開放委員会』を結成、創立85周年を迎える今年、改めて開封式典を開くことを決め、準備を進めていた。
式典には当時の在校生らを集め、重機を使ってカプセルを掘り起こして開封。一部を校内に展示し、在校生に見てもらう。
当時の在校生は現在30~37歳と、社会の一線を支える働き盛り。送付先が分からず、卒業当時の住所に郵送するしかないため、同委員会の広報担当者は「一人でも多くの人に立ち会ってもらいたいが、どれくらい集まるかは分からない』と不安を募らせる。
同委員会メンバーで、当時6年生だった主婦、増輪照美さん(36)は『長女が錦糸小学校の4年生なので、昔の写真を一緒に見て、地域のことを教えたい。同級生のうち連絡が取れそうなのは半分ぐらい。インターネットの掲示板に書き込んだりして、みんなが集まれるよう努力したい』とは話していた。
錦糸」という町名は、かつてあった「錦糸堀」という堀の名前に由来しています。錦糸堀は江戸時代、現在の北斎通りを流れていた南割下水のうち、大横川から東側の部分についての呼称で、堀だけでなくその周囲の地域も含めてそう呼ばれていました。明治5年(1872)にできた「本所錦糸町」という町名は、錦糸堀に沿った地域ということから名付けられたものです。その後、明治44年(1911)には「錦糸町」、昭和42年(1967)には「錦糸」となり、現在に至っています。
本所地域一帯は、江戸時代の明暦の大火後に開発された土地で、そのほとんどは武家屋敷でした。現在の「錦糸」にあたる地域も例外ではなく、明治維新のころは、酒井右京亮(若狭小浜藩)の中屋敷、柳沢民部少輔(越後黒川藩)の下屋敷などがありました。
錦糸町駅北口遺跡(錦糸1-35)は、旗本大嶋家の屋敷と信濃小諸藩牧野家の下屋敷の一部にあたります。ここからは数々の貴重な遺物が出土していますが、その中でもとりわけ貴重なものが、大嶋家の跡から出土した木製大小暦です。
江戸時代は、今とは違う暦(旧暦)が使われていました。旧暦では、大の月(30日)と小の月(29日)とがあり、その組み合わせが毎年違っていました。この大小暦は大の月と小の月を区別するために使われていたものです。上部に穴があけられているので、壁などにかけて使われたものと思われます。このような木製の暦が出土するのはきわめて珍しく、大変貴重であることから、墨田区の登録有形文化財にもなっています。
江戸時代の伝説「本所七不思議」の一つに「おいてけ堀」の話があります。この堀で魚を釣った人が帰ろうとすると、堀の中から「おいてけ、おいてけ」という声が聞こえ、魚を持ったまま帰ろうとすると、必ず釣った魚がなくなってしまうという話で、本所七不思議の中でも特に有名なものです。
この「おいてけ堀」がどこにあったのか、さまざまな説があってはっきりしませんが、現在の錦糸町駅近くだったという説もあります。伝説なので、場所はもちろん話の真偽も定かではありませんが、こうした伝説が伝えられていることから、江戸時代の錦糸堀はかなり寂しい場所だったことが想像できます。
大正12年(1923)9月1日の関東大震災は、東京に大きな被害をもたらしました。そしてその後、大規模な帝都復興事業が実施されます。その目玉の一つになったのが公園の整備で、これによって三大公園と52の小公園がつくられました。三大公園とは隅田・錦糸・浜町の3つで、うち2つが現在の墨田区域に設けられました。
錦糸公園(錦糸4-15-1)は、旧陸軍省糧秣廠跡地につくられたもので、芝生と花壇を主体とし、運動場もありました。本所・深川方面の工業地帯の労働者やその家族などの憩いの場でしたが、空襲の被害を受け、一時はその犠牲者の仮埋葬地ともなりました。
戦後は再び公園として整備され、現在、体育館や野球場、プールなどを備えた区立公園として多くの人に利用されています。
■江戸時代は武家屋敷
本所地域一帯は、江戸時代の明暦の大火後に開発された土地で、そのほとんどは武家屋敷でした。現在の「錦糸」にあたる地域も例外ではなく、明治維新のころは、酒井右京亮(若狭小浜藩)の中屋敷、柳沢民部少輔(越後黒川藩)の下屋敷などがありました。
錦糸町駅北口遺跡(錦糸1-35)は、旗本大嶋家の屋敷と信濃小諸藩牧野家の下屋敷の一部にあたります。ここからは数々の貴重な遺物が出土していますが、その中でもとりわけ貴重なものが、大嶋家の跡から出土した木製大小暦です。
江戸時代は、今とは違う暦(旧暦)が使われていました。旧暦では、大の月(30日)と小の月(29日)とがあり、その組み合わせが毎年違っていました。この大小暦は大の月と小の月を区別するために使われていたものです。上部に穴があけられているので、壁などにかけて使われたものと思われます。このような木製の暦が出土するのはきわめて珍しく、大変貴重であることから、墨田区の登録有形文化財にもなっています。
■本所七不思議「おいてけ堀」
江戸時代の伝説「本所七不思議」の一つに「おいてけ堀」の話があります。この堀で魚を釣った人が帰ろうとすると、堀の中から「おいてけ、おいてけ」という声が聞こえ、魚を持ったまま帰ろうとすると、必ず釣った魚がなくなってしまうという話で、本所七不思議の中でも特に有名なものです。
この「おいてけ堀」がどこにあったのか、さまざまな説があってはっきりしませんが、現在の錦糸町駅近くだったという説もあります。伝説なので、場所はもちろん話の真偽も定かではありませんが、こうした伝説が伝えられていることから、江戸時代の錦糸堀はかなり寂しい場所だったことが想像できます。
■三大公園の一つ錦糸公園
大正12年(1923)9月1日の関東大震災は、東京に大きな被害をもたらしました。そしてその後、大規模な帝都復興事業が実施されます。その目玉の一つになったのが公園の整備で、これによって三大公園と52の小公園がつくられました。三大公園とは隅田・錦糸・浜町の3つで、うち2つが現在の墨田区域に設けられました。
錦糸公園(錦糸4-15-1)は、旧陸軍省糧秣廠跡地につくられたもので、芝生と花壇を主体とし、運動場もありました。本所・深川方面の工業地帯の労働者やその家族などの憩いの場でしたが、空襲の被害を受け、一時はその犠牲者の仮埋葬地ともなりました。
戦後は再び公園として整備され、現在、体育館や野球場、プールなどを備えた区立公園として多くの人に利用されています。
錦糸町北口
錦糸町駅北口の再開発は、14年前に構想され隣接する亀戸地区と一体的に東の「副都心」として位置づけられ、平成5年11月に工事が着工し、4年の歳月をかけて完成しました。
錦糸町駅のホームに立って北口側を見ると高層ビルが壁のように建ち並んでいます。また2階部分はペデストリアンデッキ(歩行者専用通路)により、歩行者と車両が分離されておりビルの間の往来には便利なうえ、街全体にも開放感を与えています。
また、この「副都心」を挟むようにある、西の「大横川河川親水公園」、東の「錦糸公園」は人々の憩いの場所となっています。防災館で体験した後に散策なされてはいかがでしょうか。ここで一つ錦糸町の北口にある交通広場の吊り彫刻「エコー」は何を表現していると思いか。?
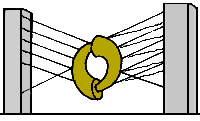
(参照:すみだの生涯学習情報「みらい」)
太平