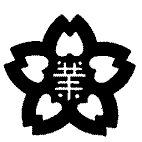|
業平小学校
(業平2- 4- 8)
開校 大正7年 3月 1日
校地面積 5179㎡
通学区域
太平1丁目17番~31番
横川1丁目全域
横川2丁目13番~20番
横川3丁目11番~14番
錦糸中学校へ
業平1丁目全域
業平2丁目全域
業平3丁目全域
業平4丁目1番~8番を除く地域
本所中学校へ
押上1丁目10番~16番、
20番~30番、
36番~43番、
48番
墨田中学校へ |
|
校歌
作詩 北原白秋 作曲 山田耕筰
1 煙(けぶり) 煙 空になびく
都の東 業平 我が校
いきおえ我等 少年市民 少年市民
学びて倦まじ
輝くもの窓辺に来たり
常に呼べり 正しく
友よ いざ 勉めん |
2 桜 桜 水に映る
隅田の春を 業平 我が校
勇まし我等 日本児童 日本児童
朝日に匂う |
3 響 響 雲にとどく
巷の誠 業平 我が校
励めよ 我等 独学自修 独学自修
進みて強し | |
教育目標と指導の重点
◎ 教育目標
人間尊重の精神を基礎に、勤労と責任を重んじ、
自主的・実践的な態度を培い、国際社会に生きる
心豊かな人間性をもつ児童像を以下のように定
め、その育成を図ります。
○健康で明るい子ども
○問題に気づきよく考える子ども
○たがいを大事にし協力する子ども
○すすんで働く喜びを知る子ども
◎ 学習指導
○基礎的・基本的事項の定着を図り、柔軟な
思考力や判断力、豊かな表現力をもつ児
童を育成します。
○各教科の中で、問題解決学習や体験的学
習を通して、自己学習力を身につけさせま
す。
○複数の教員による指導法を工夫し、個人
差に応じた指導を進め、主体的に学習す
る態度や意 欲を育てます。
○コンピュータやインターネットを各教科の
授業の中で効果的に活用し、コンピュータ
教育の充 実を図ります。
◎ 生活指導
○あいさつや言葉遣い等、基本的生活習慣
の育成・定着を図るため、各月の生活指
導目標を具現化する指導の徹底を図りま
す。
○集団生活の規律や秩序を守り、健康や安
全に留意できるようにさせます。
○事例研究会や生活指導研修会を通して、
児童理解を深め、校内の協力体制を確立
し、学校 生活上の、諸問題の早期発見・
早期解決に努めます。 |
学校概要
本校は、大正7年4月に東京市業平尋常小学校として、
中乃郷業平町に開校しました。本校の歴史をふりかえる
と、関東大震災・東京大空襲の二度にわたり校舎が焼失
するという状態に見舞われましたが、地域の方々の支援
を受け、復旧しました。昭和53年新校舎が完成しました。
本校の校歌は、作詞北原白秋・作曲山田耕作という、昭
和初期による逸材の創作です。今年は、85周年を迎え
ます。 |
鶴屋南北の世界
江戸時代を代表する偉大な劇作家には、関西に近松門左衛門、江戸では鶴屋南北があげられます。この二人は、ともに「大近松」、「大南北」と呼ばれ、映画もテレビもなかった江戸時代の人々を舞台に引きつけ、大いに楽しませてくれました。「三角屋敷」や「深川寺町」や「砂村隠亡堀」など、江東を舞台にした「東海道四谷怪談」の原作者として著名な鶴屋南北は、その評価がとみに高まっています。
南北は、怪談劇だけではなく、120本の歌舞伎脚本と20数編の合巻(紙上歌舞伎小説)を残しています。血と悪と黒い笑いにまみれた南北の作品は、人間の心の奥の地獄を見つめる鋭い眼が光っています。
その鶴屋南北は、宝暦5年(1755)、江戸日本橋新乗物町で、海老屋伊三郎という紺屋の型付職人の子として生まれた。
安永5年(1776)、22歳の時、家業を捨てて芝居の世界に飛び込んでから約30年間、作家として下積み生活をし、文化8年(1811)、57歳で4世鶴屋南北を名のります。
南北は、一時、亀戸村の植木屋清五郎の隣に借家して住んでいたことがあります。その頃、表札に「南北」とだけ書いておいたので、医者に間違えられたことがあります。後、深川黒船稲荷(牡丹町1丁目)に住みました。
江東に長く住んでいた南北は、江東を舞台にした作品を幾つも残しています。
| 門前仲町 |
心謎解色糸、曽我梅菊念力弦、盟三五切、菊月千種の夕暎、
梅暦曙曽我、とりまぜて雑石尊贐、色一座梅椿、仮名曽我当蓬莱、 |
| 深川八幡 |
心謎解色糸 |
| 平野町 |
色一座梅椿 |
| 大工町・万年橋 |
曽我梅菊念力弦 |
| 相川町 |
心謎解色糸 |
| 深川寺町・三角屋敷 |
東海道四谷怪談 |
洲崎
|
仮名曽我当蓬莱、謎帯一寸徳兵衛、蝶蝶ふたごの梅菊、
玉藻前御前公服 |
| 砂村隠亡堀 |
東海道四谷怪談 |
南北が死んだのは、文政12年(1829)11月27日、黒船稲荷の境内の家においてです。南北は死に際に、弟子たちを集め、大切なことを伝えるからといって、小さな手書きの本を渡しました。弟子たちが、劇作の秘伝を教えてくれるのかと大いに期待して開いてみると、その書き出しには、次のことが書かれていました。
略儀ながら狭うございますれど、棺の内より頭をうなだれ、手足を縮め、御礼申し上げ奉りまする。先ずは私存生の間、永々御贔屓になし下されましたる段、飛び去りましたる心魂に徹し、如何ばかりか有難い冷汗(幸せ)に存じ奉ります・・・・・
なんと、それは、南北が自分の葬式のために書いた台本だったのです。「寂光門松後万歳(しでのかどまつのちのまんざい)」という題までつけてあるのには、弟子たちも呆れてしまいました。
南北の葬式の時、歌舞伎の人気スターが、ズラリと加わり、南北のファンや見物人もつめかけたので、深川の牡丹町から本所押上の春慶寺まで、行列がひとつなぎに続いたほどでした。
命日の11月27日には、南北ゆかりの江東区で、鶴屋南北研究会によって、南北忌が行われています。
南北の おくつきどころ 石蕗の花 宇野 信夫 |
王 貞治
昭和15年(1940)5月10日、東京府向島区吾嬬町西(現墨田区八広4丁目)の中華料理店『五十番』に双子が生まれました。父は王仕福・母は登美。双子の赤ちゃんの姉は広子、弟は貞治と名付けられました。貞治の名は、登美が入院中に読んだ本、『出世物語』の主人公の名前からとりました。貞治は半ば仮死状態で生まれ、しばらくは病弱でしたが、広子が1歳3カ月で病気のために亡くなると、その代わりに貞治はみるみる元気になっていきました。
仕福・登美は昭和3年(1928)、吾嬬町西8丁目にあった中華料理店『五十番』(現在の墨田区立第五吾嬬小学校の東側)を屋号ごと居抜きで買い取り、そこで初めて店を開きました。そして昭和13年(1938)には、近くの吾嬬町西6丁目の表通り(現在の八広はなみずき通り)に面した20坪の土地に二階建の立派な店を建て移転し、貞治はここで誕生したのです。
昭和20年(1945)3月10日の空襲で焼けてしまいましたが、11月にはお店を再開し、翌年の暮には業平橋2丁目(現業平2丁目)へ移りました。これが通称『押上の五十番』です。
仕福は押上へ移転する時、「この店こそ、私達にとって最初の店だと思っている。だからここが第一、押上の店は第二・五十番にしましょう」と言って、仕福は押上の店の看板にわざわざ第二といれました。
昭和37年(1962)、仕福・登美は新宿へ転居し、そこでも営業を続けていましたが、長年働き続けた二人は昭和40年(1965)ついに店を閉めました。王貞治さんが小学校に入学したのは、昭和22年(1947)4月です。住んでいた業平地域は、業平小学校に入学する学区域でした。しかし当時の業平小学校には、第二次世界大戦の際に罹災した工場が間借りしていて、また児童の数が多かったため、教室が足りず、1・2年生は柳島小学校に間借りをした上、さらに二部授業を行っていました。そのため王さんも、業平小学校に入学しましたが、1・2年生の間は柳島小学校に通学し、3年生から業平小学校に通学しました。
王さんが野球をはじめるようになったのもこのころです。4年生の時、初めてクラスで野球チームを作り、エースで4番を務めています。5年生の時には、お店で働く店員さんに巨人対中日戦を見に後楽園球場へ連れて行ってもらいました。初めてのプロ野球観戦です。この時、巨人軍の与那嶺(よなみね)要選手にサインをもらいました。
ほかの選手がサインをしてくれない中で、与那嶺選手は快く応じてくれました。王さんがサインを断らないのは、この時の思いがあるからです。与那嶺さんは、「何で日本の選手はサインをしてあげないのか、不思議に思いました。彼が王君だったかはわかりませんが、目の大きな子供が軟球を差し出していました。
だれもサインをしてあげなかったので、僕がしたことは覚えています」と言っています。この与那嶺選手のサインが、後年の巨人軍入団に影響したことは間違いないようです。
現在、福岡ダイエーホークス監督の王貞治氏は、巨人軍時代には、独自の打撃フォームである一本足打法で、2回の三冠王、13年連続ホームラン王、通算ホームラン868号などの大記録を樹立し、初めての国民栄誉賞を受賞した不世出の大打者です。
王貞治氏は墨田区に生まれ、戦後の復興期に少年時代をむかえ、ようやく庶民に娯楽が広まり始めたころ、野球を始めました。
当時、庶民の娯楽の中心は、映画や相撲、そして野球でした。プロ野球界でも出征していた選手が復帰し、1リーグ制から2リーグ制へ、また初めてのナイターもおこなわれました。全国各地で地域や学校・会社などでチームを作り、子供から大人まで、多くのひとたちが野球に熱中したものでした。
そのような中で、高校時代には全国優勝を遂げ、またプロ野球でも活躍した王選手は、戦災で多大な被害を受けた墨田区にとって、希望の星であったといえます。
今、王貞治氏の活躍を振り返り、皆さんも僕らが野球少年だったころを思い起こしてみませんか。 |
|