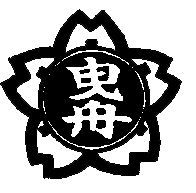|
曳舟小学校
(京島 1丁目−28番− 2号)
開校 昭和 9年 5月26日
校地面積 7141㎡
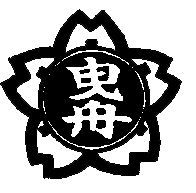
通学区域
東向島2丁目27番〜30番
京島1丁目全域
京島2丁目1番〜13番、
16番〜19番
京島3丁目1番〜10番、
31番8号〜11号〜34番4号〜10号
35番1号〜5号
曳舟中学校へ |
|
校歌
|
1 光よそそげ 明るい窓
小鳥よ歌え すずかけに
いつも希望の あふれるところ
元気で学ぶ われらこそ
墨田の誇り 曳舟校 |
2 桜と鷹に 由緒も深く
やさしくつよく この気風
町のはつらつ 力に燃えて
日本の明日の 夢が湧く
楽しいわれら 曳舟校 |
3 この技尽くし この知恵尽くし
学芸会 運動会
いつも心を ひとつにつなぎ
なかよく励み のびてゆく
栄ある 曳舟校 |
めずらしい道
京島の町の道路は、田んぼのあぜ道の名残なのかと通るたびに、カーブの多い道路だなと思っている所がある。それは、京成電鉄押上線の曳舟駅南口側の踏切を通り京島3丁目の愛国橋交番(現在の京島3丁目交番)を超えて明治通りに至る道である。
とにかく短い区間を面白いほどカーブする真っ直ぐに伸びた直線状の所が、曳舟川通りから曳舟駅南口前までしかない。後は、曲がりくねっている所ばかりである。右へ曲がると思えば、すぐ左へ曲がるという具合で、最後まで右や左へと曲がりくねっている。まさに蛇がくねっているのと同じである。
自動車で走ると、ハンドルを絶えず右に回したり左に回したり忙しい。その分、スペードも出せないが、大きな事故も起きないかもしれないから人に優しい道かもしれない。それはともかくとして、これは人が作った道ではない。-------というとオカシないいかたになるが、人間の発想で作れる道ではない。人工的に作れるはずがないと思った。
人に設計を任せたらこんな面白い道は作れない。たいてい真っ直ぐな道か、直角に交差する道で、効率的ではあるが味も素っ気もない道になること請け合い。この道は人の力を超えたものが作ったに違いない。
川が流れて、水の自然の流れに沿って出来た道に相違ない。よくテレビの画面で、北海道の釧路湿原の中を見事な曲線を描いて流れる川とかブラジルの密林地帯を流れる大河アマゾンを空撮写真で写した場面を見ることがある。自然に出来た川の流れは想いもかけぬ曲線を描いて、その不規則性が人間の想像力を超えている。創造主の造り給う芸術には人間の浅知恵では到底太刀打ちできない。
読売新聞(平成11年4月6日)に、警視庁が通学路や買物道路、子供の遊び場となる遊戯路などの生活道路に通過だけの車両を締め出す方法として、欧米のコミュニティ・ゾーンをモデルに整備に乗り出している。という記事があった。「一定の区域内で、直線道路の両脇に互い違いに植栽を置いてS字カーブ化したり「バンブ」を設けたりしている。
バンブとは高さ10〜15センチ程の路上の突起物で車が時速30キロ以上で乗り越えると、激しい上下動に見舞われるという物らしい。遅れ馳せながら人工道にもS字形道路の有難味がわかってきたように思う。
早速、地図を取り出し川の在り処を調べて見た。しかし、昭和時代には既に道路になっている。地図上では川であったという証拠になる図面も記号は出てこない。古い地図を出して見ることにした。
先ず、江戸時代の地図であるが、江戸城を中心にした江戸図が多く、本所は町奉行支配地の御府内に入るが、向島はまだ郊外周辺地区なので、ほとんど地図上に描かれてない。尾張屋版の江戸切絵図が安政3年(1856)に「隅田川向嶋繪図」を付け加えて出版したが、これは江戸後期ようやく江戸市民の行楽地となった向島の名所案内図で、地図というより文字通り絵図である。細かい部分は省略され、探している肝心の川は描かれているのか、いないのか全然わからない。
そこで、西欧の近代測量法を取入れた明治13年(1880)参謀本部陸軍測量部が測量した明治19年製版の2万分之1尺(メートルではないところが面白い)の地図「迅速図」をみた。該当する個所に川が流れていないかと見ると、案の定、川があるのが確認されて一安心した。
しかし、地図が表わしている範囲が広く、小さな地域の細かいカーブの線まで出てきていない。1尺は曲尺で約30.3センチだから、2万尺分之1尺は約6万分の1メートルにあたる。5万分の1の地図より広範囲の地域を描いてあるので細部までは分からないのは当然である。
そこで、明治12年(1879)東京府地理局地誌課発行の「実測東京全図」をみた。これには目的の川が、曳舟川から鍵状に出ているのをブルーの色を使ってハッキリ描かれてあった。川の周りには道もなく、家の点在している記号もなく、田んぼの真ん中を流れている。
更に今度は、大日本帝国陸地測量部・明治42年(1909)測図大正5年第1回修正図・1万分之1尺の「向島図」をみた。これだと大分細部までわかり、曳舟川から出ていた川は用水路のような小川となり、それに沿って南側に小径が通っている記号が付いていた。周りは水田に囲まれて、近くには向島名産の金魚養魚場とみられる大小の池が沢山あり、大分大きい池が2つあるのがわかる。江戸時代から向島は金魚の養殖が盛んだったというから明治時代までは残っていたのだろう。
この川は地図上でみるかぎり用水路になっているが、曳舟川より古い流れであったと思われる。曳舟川は江戸時代、明暦の大火後の万治元年(1658)に本所・深川の開拓のため竪川、横川を開鑿(かいさく)した時、同時に上水道として作られたものである。それに対して、隅田川の平作堀入江、いま、交通公園になっているところから地蔵坂通りには、古代から川が流れていた場所である。
明治の地図では用水堀になっているその川は、元はその支流で、曳舟川を作った時に、それを取込んだと思われる。取り入れ口の所だけ(現曳舟文化センターの横から京成曳舟駅踏み切りまで)直角に真っ直ぐ曳舟川に入っているが、堰でも作った跡を表わしている。京成線の踏切りを超えると途端に曲線模様を描き始めるから、元は川が流れていた事をハッキリ証明している。
ところで、二つの大きな養魚場の跡であるが、一つは京島3丁目の大体23番地を含め、39〜42番地辺りになる。もう一つは京島3丁目17番地の辺りと八広2丁目2,3,7,11,12,14番地辺りが、すっぽり包み込まれるほど大きい。
さて、用水堀路に沿った小径であるが、大正10年(1921)第2回修正向島図、大正14年(1925)部分修正向島図では、小径が里道に昇格し、その北側の用水路の方が脇役のように附属した溝川になっている。でもまだ周辺の田んぼや養魚場はあまり変化もなく相変わらず健在であることがわかる。
それが昭和5年測図の空中写真測図では、がらりと様子が変わり、地図上では用水路の記号が見えなくなり、それに代わって、里道が3メートル以上の町村道に成長している。道の周辺部も田んぼはなくなり、家がびっしり建ち並んでいる。養魚場のいくつかは、まだ残っているが、その周りは空地が少し残っている程度で、すっかり家屋密集地に変貌している。
考えて見れば、この間に大正12年(1923)の関東大震災があった。その後の復興がいかに向島の地を急変させたかが地図の上でも表れている。もっとも、震災後向島地区は、田畑が多く土地代、家賃が安かったのでやたらと不規則に家が建ち並んで、復興-------といってよいのかわからないほど田畑が失われ緑の自然環境は悪化したのである。
ここで、震災前後の向島地区の様子を書いた史料があるので紹介したい。隅田町が昭和7年(1932)に東京市併合記念号として発行した「隅田町誌」である。その産業の章・68ページに、当時の隅田(寺島、吾嬬も同じ状況だと思うので向島地区として一括して考える)について次のように書いている。
「本町は低温にして河川に恵まれてゐるため、明治30年までは相当農も業営まれ、また、若宮方面(今は荒川放水路の中に消えている)には土1升金1升と言われた東京へ、壁土、土蔵の土等を運搬す可(べ)き舟乗りが多数住んでゐたが、近代工業の躍進と東京の発展とは、地代の低廉にして水運の便利な此の方面を工業敷地として選ぶに至り、現在は80有余の大小会社工場があり、かって龜田鵬斎(かめだほうさい、江戸中期の儒者)をして水晶村と詠ぜしめた地も、今は、大煙突が天に向って一列砲口を敷き、太陽を蔽い隠せと許り黒煙を放射している。此の素晴らしい工業の発達に伴われて、各種商業も発達したが、水産業、林産業は絶無であり、極微小ながら畜産業がある」赤い字の部分、「低温にして・・・」という部分であるが、水辺が多く緑豊かな環境があったことを意味しているのだろう。「今は大煙突・・・・」は、富国強兵時代の風潮が表れて、いろいろな意味で面白いので強調して見た。これを読んでも、いかにこの時代の変化が激しいものであったかがわかる。
また、昭和5年に隅田町誌編纂會が発行した別誌「隅田町誌」には、向島地区は「関東大震災では隣接地として焼失を免れた故に、急場の間に合わせ的に移転し来た者が多かった」と書いている。
向島は古い街だけに思い切った大規模な都市計画が出来なっかったことに。ついては前にも書いた。その点、マイナス面も大きかったのも事実で、家が立て込み奇麗な街とはいえないのも。現実であるしかし、他の街にはない良い点がある。昔のままの道・自然が作った道が残っていることである。大正・昭和前期の町並みのモデルが残っているということである。ある意味では歴史の1ページが現実に存在しているといえる。凡てを残せとはいわぬまでも、今後区画整理や街並み整理をする場合でも、あの曲線の道は壊さないで生かして欲しい。何処へいっても同じような特徴のない直線道路と四角い箱型のビル、マンションが並ぶ街にして欲しくない。
向島が折角描いた自然の味合いのある風景をなくしてはならない。向島という水田地帯でなくては生れない地域固有の川が作った道。いわば向島の顔である。現在の経済第1主義の時代では、効率の悪い道は作れないかもしれないが、自然が描いた軟らかい温もりのある道を残す心の余裕は持ってもらいたい。
一寸余談にそれたが、前記・川道のその後の変化であるが、昭和16年(1941)発行「向島区」(発行所・日本統制地圖株式会社・縮尺9千分之1メートル)の地図には、町村道は文字通り道路になり、その北側に一条線で辛うじて水路が流れて京島1丁目51番地に残った養魚池に入っている。ところが、その道路北側沿いの現在京島3丁目14番地16号にずっと住んで理髪店を営んでいる吉岡さんの話では、「家の前は道路の半分くらいはドブ川で、橋が渡してあった。それが昭和30年、31年頃には埋立てられ、細い下水に変わったが、今は、それも下水管にして埋立てなくなった」とのことである。その後、地形図の記号について調べたら、実幅7・5メートル以下の川・水路は一条線で表示することがわかる。
今は道路だけで、そこに川があり橋があったという形跡もないが、愛国橋交番でお巡りさんに聞いたところ、元は愛国橋ではなく「相生橋」といっていたそうである。この方がよっぽど情緒のある良い名前のように聞える。また、「虎橋」という橋もこの辺あったらしいと付け加えてくれた。この辺は田んぼの溝川の多いところであったことを物語っている。
いずれにせよ、このように、この道は歴史的には古い道ではないが、古い川が流れて周囲の田んぼや池家に生命の恵みを注ぎ入れていた。その流れに沿っていた細い堤の道がだんだん産業経済の時代要求に合わなくなり陸運の道路になった。向島の歴史を無言で語る道である。だから、通るたびになにか。人間の優しさを感じさせる道になっている。
江戸時代は田んぼの大事な用水路として使われ、明治になりやがてその堤の道が道路になり、地元の人々が代々使ってきた。この自然の道を失うことなく、人と自然の豊かな暮らしの関係を思い出すためにも墨田区にいつまでも残していきたいものだ。 |
東京大空襲
1945年(昭和20年)3月10日の東京大空襲は、約2時間半余りのアメリカ軍の爆撃により、墨田区域を含む下町全域で、死者約10万人、焼失家屋約27万戸、被災者約100万人という甚大な被害を出したと言われています。
墨田区には、今も、心の奥底に空襲の記憶を刻む数多くの人々が暮らしています。そして、その記憶を後世に伝えて欲しいとの願いから、100点以上に及ぶ戦時下の資料が区に寄せられています。それらの資料は、罹災証明書などのような、直接、空襲の被災を伝えるものばかりではなく、防空体制や統制経済に関わる戦時統制下の生活をしのばせるもの、また、満州事変や日中戦争などに従軍した出征兵士関連資料など、その種類は多岐にわたっています。
これら墨田区に寄贈された戦時下の資料を一堂に展示し、人々の戦争体験と記憶がいかなるものであったのか、また、下町に暮らした庶民1人1人に戦争は何をもたらしたのか、その意味について考えてみたいと思います。
なお、1945年(昭和20年)3月10日の東京大空襲に関わる原体験が、多くの人々の戦争の記憶と認識を規定しているという点を鑑みて、はじめに東京大空襲の実相を人々の戦時体験と人々の個々の空襲体験をしのばせる思い出深い品々を、「学童疎開」、「軍隊と出征」、「戦時下の統制生活」、「戦時下の組織」というテーマに類別して紹介し、大局的な時代状況に関わる資料にこめられた「個人」としての戦争体験や「思い」が浮かび上がる「個人」の体験と記憶を抜きにして戦争の実相を把握することはできない。と、いう過去の戦争の惨禍を真摯に見つめ、未来につなげていく平和の一里塚としての役割をいささかでも果たすことができるよう、切に希望いたします。 |
橘館通り
通りの名称は、昭和6年に「橘館」という映画館がこの通りにできたことに由来しています。「橘館」は昭和36年(1961)に全焼しました。
今でも、それほど広くない道路の両側にお店がびっしりと並んでいます。中には、お惣菜屋や生鮮食料品店はもちろん、交番、郵便局、パチンコ屋、美容院まで。ここに来れば、朝食から夕食まで一日中のおかずが揃うのではないかと思うほどお惣菜の種類は豊富で、焼き鳥屋、おにぎり屋、佃煮屋、天ぷら屋、コロッケ屋などが並び、しかも、どれも安いです。

昭和36年(1961)7月15日撮影 |

平成14年(2002)7月23日撮影 |
昭和30年代はじめの墨田区内には、国鉄総武線のほか、東武線・京成線・都電・バス・トロリーバスが走っていました。主要道路には、都電やトロリーバスの架線が縦横に張り巡らされ、庶民の足として活躍していました。また、昭和35年(1960)には、都営地下鉄1号線(浅草線)が京成線との相互乗入れによって開通し、都心へ出るのがさらに便利になりました。
そして、昭和30年代に到来したマイカーブームは、今日の「クルマ社会」を生み出しました。道路の拡幅・舗装が進み、曳舟川は埋立てられて、道路となりました。
昭和36年(1961)には、首都高速道路6号線の工事もはじまりました。自動車を中心としたスピード優先の時代へと進む一方で、自動車の急増は、排ガス公害や交通渋滞、悲惨な交通事故の急増を引き起こしました。排ガスによるスモッグが空を覆うようになり、交通事故を防止するためのガードレールや横断歩道橋がこの頃から設置されるようになりました。
そして、自動車と道路を共有していた都電とトロリーバスは、交通渋滞の頻発からダイヤが不規則となり、昭和47年(1972)11月までに都電荒川線を除くすべての路線が廃止となりました。
自動車をめぐる渋滞や事故、排ガスの環境問題は、40年経った今日もなお課題となっています。
|
東武鉄道と京成電鉄
墨田区内で鉄道同士が一番接近しているのは東武鉄道と京成電鉄の曳舟駅である。また、平成15年3月19日には営団地下鉄半蔵門線が東武曳舟駅まで相互乗り入れで開通する。
東京と上毛地方とを結ぶ鉄道として、明治中期に南葛の一端に文化の息を吹きこんだ最初のものである。
明治35年4月北千住〜吾妻橋(現在の業平駅)間が延長開通するに及んで、はじめて向島地区にも鉄道が敷設され、、すでに開通していた久喜までの直通運転が実現した。
しかし、この鉄道建設は、当時の南葛飾郡隅田村と寺島村の住民にとっては、仰天するような事件であった。
此の辺は先祖代々の農家で、ごく単調な仕事にいそしんでいる極楽郷であったが、そこへ突然、脚絆(きゃはん)わらじ姿で、赤白だんだらの棒を担ぎ、測量器具を携えた連中が大挙してやってきてのでる。
これが何と東武鉄道の測量隊なのだが、先祖伝来の土地がなくなると、住民が驚いたのは無理もないことだった。そこで関係者は、会合を重ねたり、村長宅に押しかけたり・・・・・・・・・・。
ところが、いよいよ土地買収となると、その頃で、3.3㎡(1坪)の買収価格が、田が3円、畑が4円、宅地が5円と、破格の高値なのに重ねて驚いたという。
その後、明治37年4月に曳舟〜亀戸間が開通し、総武線に連絡、この頃終着駅であった川俣(埼玉県内)まで、亀戸から直通運転をおこなった。そのため、一時は、曳舟〜吾妻橋間が廃線となったが吾妻橋駅を浅草駅と改称し、明治43年3月復活した。
昭和6年3月12日浅草駅〜浅草雷門間が高架で線で延長され、昭和2年に開通していた地下鉄線との連絡が実現、上毛地方と都心との交通が完成したものである。
京成電鉄は、大正元年11月に押上〜江戸川(柴又)間が、まず開通し、以後、柴又〜金町、江戸川〜中山、と順次延長して、大正10年7月押上〜千葉間が開通、更に大正15年12月津田沼〜成田間が完成し、全線開通したものである。
しかし、京成電鉄では、これに満足せず、都心乗り入れを図って押上〜上野間など種々路線計画を立てたが、いずれも認可が得られず実現しなかった。
この計画のひとつに、向島から白鬚を経て千住に至る路線があった。この線は、白鬚〜千住間が認可が得られないまま、昭和3年7月向島〜白鬚間を開通させたが、延長の見込みが立たず、昭和11年2月末には早くも廃止された。
この京成電鉄玉の井停車場付近の模様を、永井荷風は「おもかげ」(昭和13年)の中で次のように記している。
「線路に沿う売貸地の札を立てた広い草原が鉄橋の架った土手際に達してゐる。去年頃まで京成電車の往復してゐた線路の跡で、崩れかかった石段の上には取払はれた玉の井停車場の跡が雑草に蔽われて、此方から見ると城址のやうな趣をなしている。
わたくしは夏草を分けて土手に登って見た。眼の上には遮るものもなく、今歩いてきた道と空地と新聞の街とが低く見渡せるが、土手の向側は、トタン葺の陋屋が秩序もなく、端(はて)しもなく、ごたごたに建て込んだ間から湯屋の烟突(えんとつ)が屹立して、その頂きに7、8日頃の夕月が懸ってゐる」。
なお、京成電車都心部乗り入れは、昭和5年10月、筑波高速度電気鉄道を合併し、青戸から上野への乗り入れを達成し、また、昭和35年12月には押上で都営地下鉄線との相互乗り入れが実現、利用者に大きな利便を与えている。 |
|